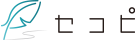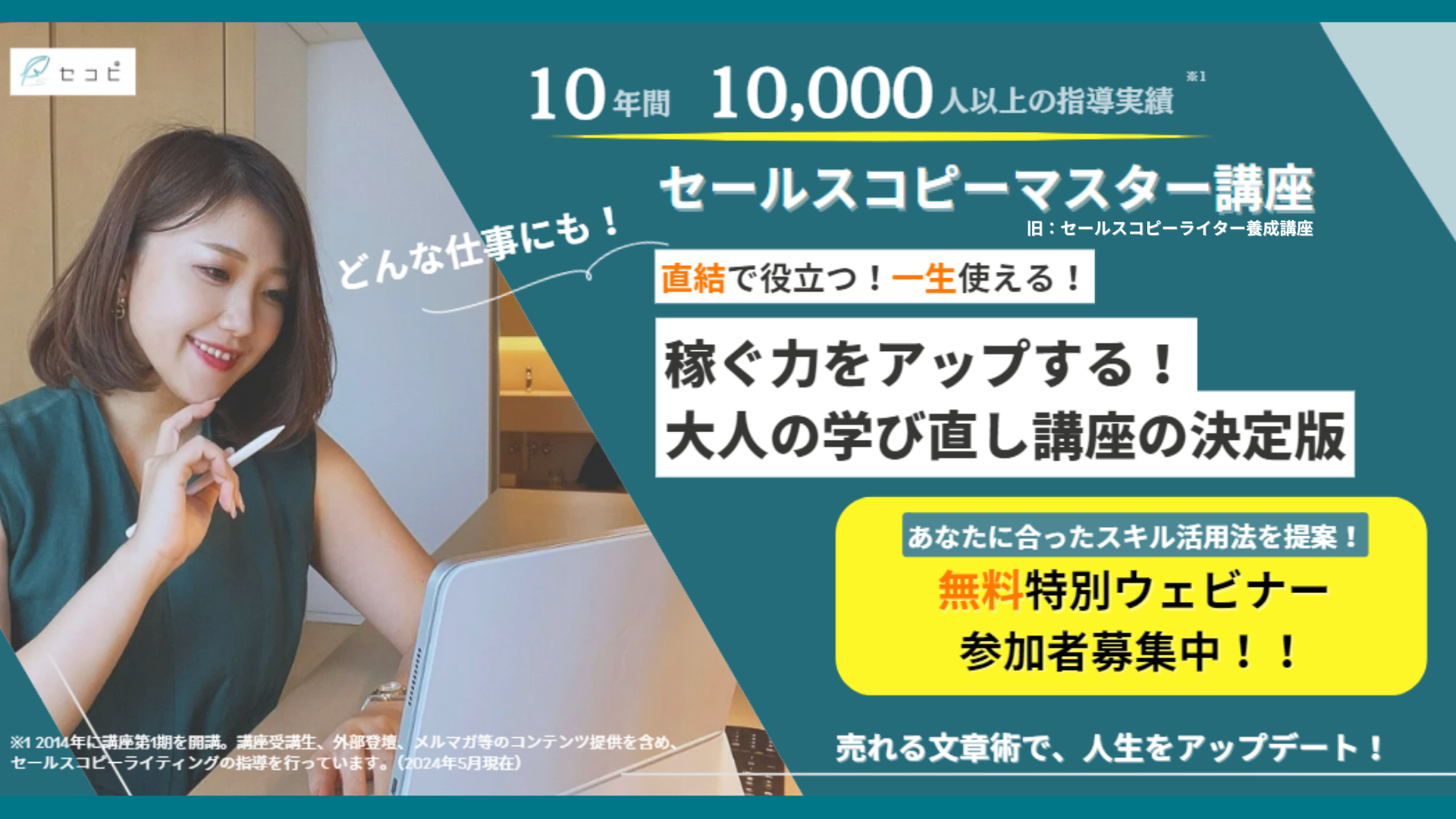ライターの確定申告と節税をFPが解説。本業ライターも副業ライターもしっかり納税をしましょう!

専業でも、副業でも、ライターとして稼ぎ始めたのであれば、毎年3月15日までに所得税の確定申告を済ませなければなりません。
ライターやフリーランスとして仕事を始めた方にとっては、初めての確定申告。
「確定申告って、何をどうしたらいいの?」
「私は確定申告が必要なの?」
「できる節税があれば利用したい」
「ライターじゃないけど、確定申告について知りたい」
という方のために、AFPと簿記の資格を持つライター・鈴木恵理が、確定申告と節税について、わかりやすくお伝えします。
尚、この記事は、2024年12月24日時点の情報で書かれています。最新の情報は、必ず国税庁HPや税務署、税理士等に確認してくださいね。
そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の個人の所得を計算し、そこから納税額を算出して、税金を正しく納めることです。翌年の3月15日までに、住所地のある税務署に申告書を提出します。
会社員であれば、会社で年末調整を行うことで、給与所得分の税金が正しく納税できます。
しかし、副業でライターなどをしている場合や、医療費などの控除を受けたいときには、確定申告をしなければなりません。
また、税金を正しく納めることが目的なので、払い過ぎていた場合には確定申告をすることで、還付金として返金してもらえます。
例えば、6月までは会社員をしていて退職。その後、フリーランスになった方の場合、6月までは昨年の年収をもとに計算された税金を給与から納めているので、会社員のときよりも稼いでいなければ税金が戻ってきますよ。
確定申告が必要かどうかを判断するところから、ひとつひとつ順番に、わかりやすく解説していきますね。
あなたのライター業は本業?副業?
あなたが開業届を提出し、本業としてライターをしているのであれば、確定申告は必要です。ライターとしての報酬は、事業所得として得られた収入(報酬)から、かかった経費を差し引いて算出します。
事業所得(利益) = ライター収入 − 経費
このとき事業所得が少額やマイナスの場合でも、必ず確定申告をしましょう。理由は、青色申告*事業者の場合、損失(マイナス)を3年間繰り越せるからです。つまり、今年のマイナス分を、来年以降の利益から引けるのです。
(*後半の【事業所得の「青色申告」と「白色申告」の違い】でご説明しています。)
会社員などが本業で、副業としてライターをしている場合は、事業所得または雑所得としてライター報酬の確定申告をします。開業届を出していない場合は、事業ではないため雑所得となり、経費を差し引いた利益が20万円を超えた場合が対象。但し、ライター以外にも雑所得がある場合には、それも含めて判断することにご注意ください。
雑所得(利益) = (ライター収入+他の収入) ― 経費
雑所得については、国税庁HP:雑所得をご覧ください。
事業所得と雑所得の違いは?
大きな違いは、開業届を提出してライターを事業として行っているか否かです。
日本では、所得を①給与 ②事業 ③利子 ④配当 ⑤譲渡 ⑥不動産 ⑦一時 ⑧退職 ⑨山林 ⑩雑所得の10種類ごとに計算するルールのため、事業じゃない場合のライター報酬は⑩雑所得になります。
事業所得と雑所得は、どちらも経費を使えます。しかし、利益ではなく損失が発生した場合に、事業所得であれば他の所得と損益通算をできるというメリットがあります。
【事業所得と雑所得の違い】
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
|---|---|---|
| 開業届の提出 | 必要 | 不要 |
| 確定申告 | 必要 *1 |
20万円以下の場合は不要 *2 |
| 他の所得との損益通算 | 可能 | 不可 |
*1:事業所得が48万円以下の場合にはしなくても良いという指南書もありますが、損益通算ができるので、マイナスの場合でもしたほうが良いという意味で必須と記載しております。
*2但し、雑所得が20万以下でも、他の所得の申告や控除(医療費・住宅ローンなど)を受ける場合には、確定申告をします。
開業届の出し方は、国税庁HP:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続をご覧ください。
ライターにはどんな節税ができるの?節税と脱税の違い
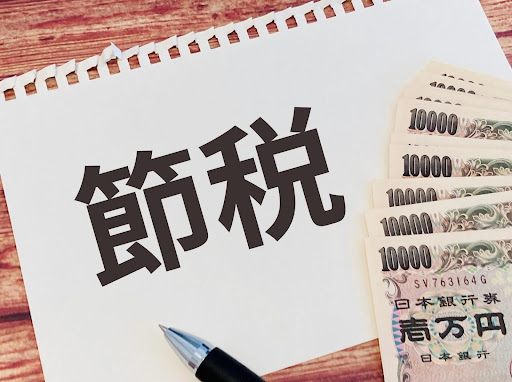
最初に、「節税」と「脱税」は大きく異なります。
「節税」とは、税制で許されている範囲で、収める税金が少なくなるよう工夫することです。
一方、「脱税」は売上を少なく申告して納める税金を減らしたり、納めないようにしたりする違法行為です。そのため、見つかったときには納めるべき税金に加えて、延滞税などの罰則金を支払うことになりますし、金額によっては刑事罰を受けるので、絶対にやめましょう。
ライターの節税その1:控除の確認
まずは控除の利用です。控除は社会政策上の要請や、納税者の個人的事情に配慮した制度で、所得から差し引いて税負担を軽減します。医療費などの「物的控除」と、扶養する親族に関わる「人的控除」があります。
それぞれ該当すれば、所得から引くことができますよ。下記をチェックしてみてくださいね。
【物的控除】
- 雑損控除:災害などで家屋等の資産に損失が発生したとき
- 医療費控除:医療費10万円以上(所得200万円以下の人は所得の5%以上)または医薬品を12,000円以上負担したとき
- 社会保険料控除:国民年金、健康保険の自己負担分
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業や個人事業主向けの退職金のようなもの
- 生命保険料控除:生命保険、医療保険、個人年金保険の掛け金の一部
- 地震保険料控除
- 寄附金控除:ふるさと納税など
小規模企業共済は、将来のために貯めた金額(月額1,000円から70,000円のため年間最大84万円)の全てを所得から控除できます。生活資金に余裕のある方には、おすすめですよ。
また、小規模共済とは別に、iDeCo(イデコ)という個人年金制度では、節税しながら資産を形成することができます。年金なので、原則60歳まで引き出せませんが、個人事業主は月額6.8万円(年間最大81.6万円)を掛金にして、全額を所得から控除できます。
iDeCoについて詳しくは、こちらをご覧ください。
【人的控除】
- 障害者控除:ご自身または配偶者、扶養親族が障害者の場合
- 寡婦控除:夫と死別し、または離婚した後婚姻をしていない人で、扶養する子のいる人
- ひとり親控除:ひとり親で、扶養する子のいる人
- 勤労学生控除:働きながら学校に在籍している人
- 配偶者控除、配偶者特別控除
- 扶養控除:16才以上の親族を扶養している人
- 基礎控除
障害者控除以外の人的控除には、本人または扶養親族の所得金額による制限があります。
それぞれの控除について詳しくは、国税庁HP:所得控除のあらましを参照してください。
ライターの節税その2:経費の見直し
仕事に必要な費用は、経費として計上することができます。例えば、下記のようなものが認められているので、経費にできるものがないか、見直してみてください。
- 家賃、通信費:自宅を仕事場として使っている場合、一部を経費にできます。家事按分といい、全体を100%としたときに仕事とプライベートの割合を決めて、計上します。
- 新聞図書費:取材や執筆に必要な書籍や雑誌の費用
- 消耗品費:仕事に必要なパソコン、ICレコーダー、文房具などの費用
- 旅費交通費、会議費:取材や打ち合わせで外出したときの交通費や、コーヒー代など
- 研修費:スキル習得のための講座費用
- その他:ソフトウェアの代金や、月額サービスの利用料
経費として計上できそうなものはありましたか?
経費にするためには用途と金額を証明できるレシートや領収書が必要です。面倒でも、捨てずに保管しておきましょう。
確定申告の大まかな流れ

ここからは、確定申告をする人向けに、解説していきます。
「今年は確定申告をしない」という方は、来年度以降の参考にしてください。
おおまかな流れは、次の4ステップです。
- 10種類の所得ごとに1年間の収入と経費を集計し、収入−経費で、所得金額を出す
(①給与 ②事業 ③利子 ④配当 ⑤譲渡 ⑥不動産 ⑦一時 ⑧退職 ⑨山林 ⑩雑所得) - 支払った社会保険料、保険料、個人年金(iDeCoなど)、住宅ローン、医療費など、控除の申請に必要な金額がわかるものを用意
- 確定申告のフォームに入力し、申告書類を作成する
- 住所地のある税務署に3月15日までに提出をする
シンプルに言えば、確定申告に必要な数字を集めて、フォームに入力して提出するだけなのです。
しかし、初めての方にとっては、難易度の高い無理ゲーのように感じてしまうかもしれません。私も最初のときは「初めての確定申告」的なガイド本を読んで、ドキドキしながら書類を提出しました。
ここから先を読んでいただければ、やるべきことがわかるので、安心してくださいね。
事業所得の「青色申告」と「白色申告」の違い
事業所得の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告をするには、「青色申告承認申請書」を提出します。そして、日々発生するお金のやりとりを帳簿に残すなど、少し手間をかけることで、最大65万円の特別控除を受けることができるのです。控除は事業所得(利益)からそのまま引くことができるため、税金を計算する基になる金額を下げることができて、節税にもなりますよ。
その他にも、以下のメリットがあります。
- 青色事業専従者給与(専任で手伝う家族に賃金を払い、経費にできる)
- 貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)を経費にできる
- 純損失の繰越し(翌年から3年)、前年への繰戻しができる
もっと詳しく知りたい方は、国税庁HP:青色申告制度をご覧ください。
税務署は確定申告をサポートしてくれる
税務署というと、「税金の取り立てをする所」というネガティブなイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし、実際は私達が税金を正しく申告し、納められるようにサポートしてくれる役割を担っているので、色々と親切に教えてくれます。
確定申告の時期になると、地元の税理士会と一緒に、相談会も開催されるので、不安な方は行ってみるのもおすすめです。住所地のある税務署は、こちらで調べられます。
確定申告書とは?
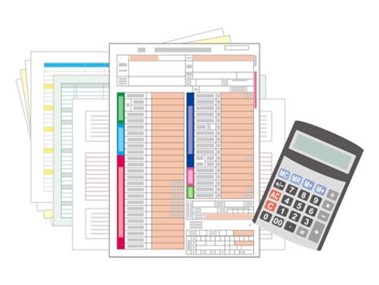
確定申告の大まかな流れがわかったところで、確定申告書の作り方を理解しましょう。
確定申告書は1枚じゃない!
確定申告書とは、確定申告のときに提出する書類のうちの1つです。実際には、下記のように複数の書類を提出します。
【確定申告で提出する書類(青色・白色別)】
| 書類の名称 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 確定申告書*1 (第一表、第二表の2枚で構成) |
◯ | ◯ |
| 第三表 | ◯*2 | ◯*2 |
| 第四表 | ◯*3 | ◯*3 |
| 青色申告決算書 | ◯ | ― |
| 貸借対照表と損益計算書 | ◯ | ― |
| 収支内訳書 | ― | ◯ |
*1:2021年(令和3年)分までは申告書の様式がAとBの2種類ありましたが、2022年(令和4年)分より、様式は統一されています。
*2:分離課税の所得(④配当 ⑤譲渡 ⑥不動産 ⑧退職 ⑩雑所得)がある場合
*3:事業に限らず、損失を申告する場合
事業所得の確定申告書類の作成に必要なもの
事業所得について、提出する書類を作成するためには、それぞれ準備が必要です。
冒頭でも触れた、事業所得を正しく把握するために、ライター業に関わる入出金を自分で記録しておいたものがこれらに該当します。
つまり、ライター業に関わる入出金は、指定された方法に合わせて記録する必要があるのです。
ここで紹介する内容は、簿記や会計の知識が無い方には、見慣れない言葉だらけかもしれません。
しかし、初めての方でも、簡単に準備できるように、会計のクラウドサービスや、会計ソフトがあるのでご安心ください。誰もが正しく納税できるように、各種サービスが充実していますよ。
【提出する書類の作成に必要なもの(青色・白色別)】
| 書類 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 帳簿 (青色は複式簿記、白色は簡易簿記でもOK) |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 法定帳簿(収入や経費を記載)、任意帳簿(法定以外の帳簿) |
| 決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 棚卸表など決算で作成した書類 |
| 現金預金取引の関係書類 | 領収証、小切手控え、預金通帳、借用証など | 同左 |
| その他 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 同左 |
これらの書類は、提出する必要はありませんが、一定期間(5〜7年)の保存が義務付けられています。
詳細は、国税庁HP:記帳や帳簿等保存・青色申告、または白色申告の方の記帳・帳簿等の保存制度をご覧ください。
事業所得の申告以外に必要な書類や準備
事業所得は、10分類された所得のうちの1つです。それぞれの所得ごとに、必要な書類が決まっています。また、控除を受けるときにも、それぞれ必要な書類があります。
国税庁で毎年1月に確定申告の特集ページが開設されるので、最新の情報をご確認ください。
・令和6年分の確定申告特集ページ
確定申告書類の作成と提出方法

確定申告書類の作成方法は大きく3タイプ。
【パソコンまたはスマホで作成】
- 国税のe-Tax(電子申告)のホームページから入力
- 会計ソフトを購入し、会計ソフトに入力
- 会計クラウドサービスを契約し、会計クラウドサービスに入力
【手書きで作成】
- 税務署で配布されている専用の用紙に記入
【税理士に依頼して作成】
- 税理士に依頼(多くの場合、会計ソフトやクラウドサービスを利用しています)
また、提出方法も、作成した方法によって選べます。
| 作成方法 | インターネット | 郵送 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| パソコンまたはスマホ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 手書き | ― | ◯ | ◯ |
| 税理士 | ◯ | ◯ | ◯ |
おすすめの方法
簡単な方法として私がおすすめするのは、会計クラウドサービスを契約して、インターネットで提出する方法です。入出金や請求書の情報を入力していけば、帳簿類や損益計算書などの必要書類を作成できるからです。
いくつも種類はありますが、私はfreee(フリー)。わからないことがあっても、チャットで聞いて解決できる点、手順に従って入力すれば、確定申告の書類を作成し、そのまま提出が完了する点が気に入っています。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
数字に苦手意識をお持ちの方でも、文章の読み書きができて、情報整理が得意なライターであれば、確定申告の作業は難しくありません。
日頃からお金の出入りをこまめに記録し、早めに準備をしておけば、わからないことがあっても、税務署や税理士に相談をする時間的な余裕ができますよ。
当講座では、プロのセールスコピーライターとして必須スキルが身につくのはもちろんのこと、確定申告や簿記など、フリーランスとして知っておきたい内容のセミナーも随時開催しています。
◆過去に開催したセミナー
「フリーランスになるなら必ず知っておきたい!お金の教養セミナー」
「フリーランスのための初めての確定申告講座」
「確定申告にも使えるようになる! フリーランスのための超簡単!簿記講座」
ご興味を持った方は、ぜひこちらをご覧ください。
この記事を書いた人
 セールスコピーライター
セールスコピーライター
鈴木 恵理 ▶Facebook
商品・サービスの魅力を発見し、集客に貢献するセールスコピーライター兼マーケティングプランナー。AFP資格と簿記2級も保有しているため、金融系のライティングも得意。大手電機メーカーで、商品の販売促進、直販窓口の運営、コールセンターに寄せられるお客様の声の分析など、マーケティングに13年間携わる。 退職し、結婚。子育てをしていた時期に出会った中小企業の経営者に、集客の相談をされたことを機に、個人事業主として仕事を再開。 ベンチャー企業でSEOライティングのディレクションを経て、現在に至る。あなたの会社のマーケティング担当者”として、 中小企業や士業、個人事業主の方のプロモーションと、それに付随するLP制作、ステップメール、メルマガ、ブログなどを支援いたします。